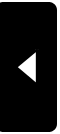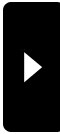2018年07月24日
'18.07.15-16 鳳凰三山テント泊縦走 後編 三山縦走~中道ルートで下山

道の駅韮崎からの鳳凰三山
03:00 スマホのアラームが鳴る。
そこかしこのテントから音が聞こえる。
山の朝は早い。
03:30寝袋から這い出す。
テント内を片付けはじめる。

04:39 テントの撤収完了
残しておいたグランドシートの上で朝食です。
昨晩一食しか食べなかった棒ラーメンを二人で食し、
簡単に済ませる。
今日は地蔵岳に上がり観音岳、薬師岳と縦走。
中道で青木鉱泉に戻る予定だ。

テン場もずいぶん人が減ってきた。
テントをそのままにして御来光を見に行ってる人達もいるみたい。

鳳凰小屋は何棟か建屋が有り敷地的にはまあまあ広いかなと。
日中電気は付けていないっぽく内部は暗い感じでした。
昔ながらの山小屋というか本来あるべき姿の山小屋なのかもしれません。
特筆すべきは豊富な水量の水場でしょう。

05:22 地蔵岳に向かって出発です。
地蔵岳まで1.0kmですがコースタイムは1時間20分です。
コレが意味することは後ほど思い知ることになります。

白ザレの崩落地が見えてきました。
これからどんな光景が待ち受けているのか、
俄然テンションが上がります。

ここから白ザレエリアに突入。
斜度がハンパないうえに日が昇ってきて焼かれます。
辛い!
背中からと白ザレの反射ではさみ焼き状態です。
サングラスないとかなりキツイかも。

白ザレの急登、登っても登っても全然上がりません。
前情報で知ってはいましたがまさかこれほどとは・・・
鳳凰小屋から距離1kmでコースタイム1時間20分の理由がここにありました。

オベリスクまであと少し、
なのですがそのあと少しがなかなか届かない。

06:36 一応地蔵岳2764m登頂?
ここからは容量圧迫覚悟で高画質拡大画像でお届けします。

↑クリックするデカイ↑
オベリスク直下からの早川尾根と甲斐駒ヶ岳。
甲斐駒の迫力ったら、南アでも随一じゃないでしょうか。

↑クリックするデカイ↑
甲斐駒のアップと奥に連なる北アの稜線。
北アルプスのスーパースター達が並びます。

↑クリックするデカイ↑
鳳凰三山の象徴とも言えるオベリスク。
クライミング経験者なら残置ロープも有るので、
尖塔のてっぺんまで登れるみたいですが、
自分は途中まで。

圧倒的迫力のオベリスクとそれを見上げる自分の図。
いやあ、
来て良かった。
本当に良かった。
こればっかりは苦労して登らないと生で見ることのできない光景ですからね。

オベリスク直下の岩の隙間に咲くタカネビランジ、
和みますなあ・・・

これから向かう観音岳への稜線。
けっこう登り返すっぽいね・・・

賽の河原に出ると標柱がありました。
結局のところ地蔵岳のピークってオベリスクのことなんでしょうかね・・・

地蔵岳故に多数の地蔵群。
賽の河原でお地蔵様って霊山のソレですね・・・
ガスってたらけっこう雰囲気やばそうな感じ。

南アではお馴染みのコレがありました。

07:28 最近お決まりのポーズ、オベリスクと親指と俺。
名残惜しいですがオベリスクに別れを告げ、
アカヌケ沢の頭に上がり、観音岳に向かいます。

南アの主峰、北岳さん。
中央道側から見るのと全然違う印象です。

参考までに櫛形山('14.11.24撮影)からの北岳さん。
間ノ岳に向けてなだらか稜線が続いてるせいか穏やかに見えます。

アカヌケ沢の頭からはこんな感じの稜線です。
やはり花崗岩の白ザレです。

広めのコルに下りてきました。
観音岳までけっこう登り返す感じで少々萎えます。

コルは鳳凰小屋への分岐になっています。
地蔵岳と賽の河原をパスしてコルに直接アクセスできるようです。
初日に地蔵岳と鳳凰小屋をピストンしたなら、
翌日は小屋からコルまでショートカットっていうルートもとれますね。

富士山が見えてきました。
富士山が見えると安心するのはなんででしょうかね・・・

↑クリックするデカイ↑
地蔵岳方向を振り返って。
絶景です。
南アルプスはもっと評価されても良いと思うんですよね。
オベリスク直下の白ザレが登ってきたルートです。
斜度のきつさがわかるかと思います。

09:37 観音岳2840m登頂
自分の登山歴で最高標高を更新です。
この標高でも暑い。

上の岩場に登ってみるとここが真の山頂のようです。
360度のパノラマが満喫できました。

富士山を正面にこれから向かう薬師岳への稜線です。
観音岳2840m→薬師岳2780mなので基本下りの稜線歩きです。

観音岳から下りる稜線でTeam富士山の三名にお会いしました。
御来光を見に地蔵岳へ上がり、三山縦走して戻る途中でした。
薬師岳まで行ってまた鳳凰小屋に戻りテントを回収してドンドコ沢で下るとのことでした。
そのルート、ハード過ぎませんかね?
健脚だからこそ成せる、ただただ凄いとしか言いようが無いですね・・・

バットレスを正面にした北岳さんと白峰三山。
北岳さんの山容はとても男前だな~と思いました。
ここもいつか縦走してみたい。

富士山と薬師岳とマイハニー。
観音岳から薬師岳は右手に南アの主峰群を見ながらの、
とても気持ち良い稜線歩きです。

山体の西側を巻くので暑さからは逃げられます。
2500m超えの稜線歩きを満喫します。

10:30 薬師岳2780m登頂です。
手持ちの水が底をつきそうだったので調達しに薬師岳小屋に向かうことにします。

薬師岳から薬師岳小屋までは下りで5分ほど。
赤い屋根が薬師岳小屋です。
昨年建て直したそうです。

連休中でかなり混雑したそうで、ラスト一本の500mlのビールにありつけました。
コーラなどもあらかた売り切れで、下山して歩荷するとのことでした。
下山するまで明らかに水の残量が足りなかったので、
濾過した雨水のペットボトルを2本購入。
時間的にもちょうど良かったのでお昼にすることにします。

お昼ご飯はキノコとトマトソースペンネ。
早茹でのペンネと乾燥キノコの早、楽、旨の山ご飯です。
久々に山飯やった気がする。

11:55 若干登り返して薬師岳に戻ります。
改めて記念撮影。

薬師岳も山頂は岩頭があり地蔵岳に似た雰囲気です。
ここから中道で青木鉱泉に下ります。
一気に標高差1700mをひたすら下りるルートです。
膝が弱い自分としては一抹の不安がありますが、
ここまで来たらもう下りるより他無いので、下山開始です。
単調な登山道をひたすら下りること1時間強・・・

13:14 このルートで唯一の見所御座石(標高約2300m)に到着。
岩と地面の間に木を入れるのはどこも同じなんですね。
御座石から青木鉱泉までは2時間45分とありました。
まだ標高差1200m残っています。

中盤は若干なだらかな斜面の熊笹エリア。
なだらかなので歩行速度が上がり、
経過時間に対して標高がメリメリ下がっていきます。

14:40 青木鉱泉まで1時間40分とあります。
途中で休憩してるので歩行速度は概ねコースタイム通り。
熊笹エリアを抜けるとひたすら続くつづら折りで標高を落としていきます。

廃屋が見えてくると登山道はそろそろ終わりです。
でも高度計的にはまだまだ残っています。

16:13 林道との合流地点です。
でもここから林道で青木鉱泉まで200mほど標高を下げます。
標示では青木鉱泉までまだ40分あるとのこと。
長い!

17:12 途中で車回収したりで青木鉱泉到着。
ようやく下山完了しました。
いやあ~、過酷な下山でした。
とりあえず自販機でかろうじて残っていたコーラ350ml缶で水分補充。
干からびる寸前の身体に染みました。
距離的にはそれほど長くないのですが暑さと斜度が堪えました。
急登は下山でもキツイということを実感しましたよ。

↑クリックするデカイ↑
GPSデータ、往路(赤)、復路(緑)
標高差 不明
歩行距離 約10.0km
行動時間 11時間50分
一泊二日トータル
標高差 約2100m
歩行距離 約15.5km
行動時間 約19時間20分
天気に恵まれ最高の眺望を拝むことができました。
ドンドコ沢で登り、中道で下りましたが、どっちから回っても辛いルートだと思います。
歩行距離に対して標高差があるので平均斜度が高いのがそう感じるのかと。
それを差し引いてもおつりがくるくらいの素晴らしい山でした。
少ない登山歴ですが間違いなく百名山だと思いました。
南アはもっと評価されても良いと思うんですよね・・・

日本三大急登、北ア三大急登などの距離と標高差のグラフ。
薬師岳の中道も入っていますが、距離が短いのでなんとかなりましたが、
この斜度で倍近い黒戸尾根とか殺人的ですね・・・
色々考えを改める良いきっかけにもなりました。
現時点での体力の限界もよく分かったし。
自分はまあいいとして、
暑いなか急登のルートをマイハニーも本当によく頑張ったと思います。

一泊二日の汗を流しにむかわの湯へ。
時間的に遅かったので適当にファミレスで夕食を取り、
渋滞回避しつつ帰宅。
憧れの山に登れ達成感、充実感、最高の二日間でした。
得る物も多い山行でした。
次は夏恒例の東北遠征。